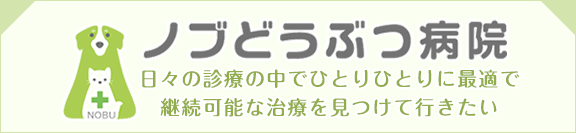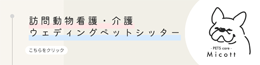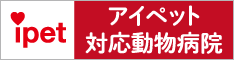- What’s new Lila
- 「花神」田中芳男
「花神」田中芳男
2013.10.26
先日一冊の本を読み終えました。
本は、百田尚樹の影法師。
日本の江戸時代の武士の生涯を描いたものです。
武士の時代の小説を読んでいると、「武士は食わねど高楊枝」という川柳の通りといつも思いますが、
今回の小説は、当時の日本人の生活が、結局はお上でもなく誰でもない、突き詰めれば、米の出来高に左右されているということに、改めて驚きました。
長い鎖国のあいだに、日本の経済は疲弊し、穫れる農作物は貧しく、土地は痩せ、
そうすると、領土も少なく、武士の生活まで貧窮するという仕組みは、驚くべきです。
さて、小説とは離れますが、皆さんは田中芳男という人をご存知でしょうか。
以前にも、ミキモトの御木本幸吉に真珠養殖を教えた人ととしてここに書いたけれど、
東京大学農学部 駒場農学校を築いた人で、また日本にあらゆる野菜、果実もろもろを齎した人です。
武士の世から、文明開化を経たとき、私たちの食卓が豊かになり、栄養価が豊富で、健康に暮らせるその礎を築いた田中芳男を覚えておいて欲しいと、切に思うのです。
先日、夏に主人と出掛けた飯田市は、いつか必ず、田中芳男の功績の一つ、林檎並木を見に行きたいと思ったのですが、林檎並木の向こうに田中芳男の為の石碑顕彰碑が建てられているのを見て、思わず涙が出たほどです(笑)
林檎を日本に齎したのも田中なら、白菜の種を日本に持ち帰り、津田梅子さんに最初にご披露したという話も、ロマンティックで素晴らしいと思うのですがいかがでしょうか。
他にも、桜の品種ソメイヨシノの発見、珈琲の栽培、オリーブの栽培・・・とその功績は数えれば切りがないのです。
私の読んだ西尾敏彦氏の 飯田が産んだ日本近代化の「花神」田中芳男 の冒頭は、こんなフレーズで始まっています。
慶応二年の夏、相模、伊豆、下総の野山などを巡り、虫取りに熱中する変なサムライがいた。慶応二年と言えば世は維新前夜の争乱の時代である。その世情に背を向けた彼の行動は、翌年パリで開かれる万国博覧会に日本の昆虫標本を出品する為のものであった。・・・(中略)・・・私は日本近代化の花神と呼ぶのが最もふさわしいと思う。花神とは中国民話に出てくる「花咲か爺さん」、野山に花を咲かせる神のことである。司馬遼太郎は小説「花神」で幕末の動乱期に近代兵制を導入した村田蔵六を花神になぞらえたが、野山に文明開化の花を咲かせた真の「花神」なら、なんと言っても田中芳男だろう。
私は、この冒頭部分が大好きです。
また顕彰碑には、田中芳男は幼少時父より、
「人たるものは此の世に生まれ出たからは時分相応の仕事をして、世用を済さなければならない」
と教えられたとありました。
父の教えを、父の思う以上に全うした日本の偉人です。
※)田中芳男さんは、私の友人の曾祖父にあたります。
欲の無いこの愛すべき友人に代わって。
(彼こそ、小説や映画にすれば面白いのに。主人公は是非、堺雅人さんに。)
本は、百田尚樹の影法師。
日本の江戸時代の武士の生涯を描いたものです。
武士の時代の小説を読んでいると、「武士は食わねど高楊枝」という川柳の通りといつも思いますが、
今回の小説は、当時の日本人の生活が、結局はお上でもなく誰でもない、突き詰めれば、米の出来高に左右されているということに、改めて驚きました。
長い鎖国のあいだに、日本の経済は疲弊し、穫れる農作物は貧しく、土地は痩せ、
そうすると、領土も少なく、武士の生活まで貧窮するという仕組みは、驚くべきです。
さて、小説とは離れますが、皆さんは田中芳男という人をご存知でしょうか。
以前にも、ミキモトの御木本幸吉に真珠養殖を教えた人ととしてここに書いたけれど、
東京大学農学部 駒場農学校を築いた人で、また日本にあらゆる野菜、果実もろもろを齎した人です。
武士の世から、文明開化を経たとき、私たちの食卓が豊かになり、栄養価が豊富で、健康に暮らせるその礎を築いた田中芳男を覚えておいて欲しいと、切に思うのです。
先日、夏に主人と出掛けた飯田市は、いつか必ず、田中芳男の功績の一つ、林檎並木を見に行きたいと思ったのですが、林檎並木の向こうに田中芳男の為の石碑顕彰碑が建てられているのを見て、思わず涙が出たほどです(笑)
林檎を日本に齎したのも田中なら、白菜の種を日本に持ち帰り、津田梅子さんに最初にご披露したという話も、ロマンティックで素晴らしいと思うのですがいかがでしょうか。
他にも、桜の品種ソメイヨシノの発見、珈琲の栽培、オリーブの栽培・・・とその功績は数えれば切りがないのです。
私の読んだ西尾敏彦氏の 飯田が産んだ日本近代化の「花神」田中芳男 の冒頭は、こんなフレーズで始まっています。
慶応二年の夏、相模、伊豆、下総の野山などを巡り、虫取りに熱中する変なサムライがいた。慶応二年と言えば世は維新前夜の争乱の時代である。その世情に背を向けた彼の行動は、翌年パリで開かれる万国博覧会に日本の昆虫標本を出品する為のものであった。・・・(中略)・・・私は日本近代化の花神と呼ぶのが最もふさわしいと思う。花神とは中国民話に出てくる「花咲か爺さん」、野山に花を咲かせる神のことである。司馬遼太郎は小説「花神」で幕末の動乱期に近代兵制を導入した村田蔵六を花神になぞらえたが、野山に文明開化の花を咲かせた真の「花神」なら、なんと言っても田中芳男だろう。
私は、この冒頭部分が大好きです。
また顕彰碑には、田中芳男は幼少時父より、
「人たるものは此の世に生まれ出たからは時分相応の仕事をして、世用を済さなければならない」
と教えられたとありました。
父の教えを、父の思う以上に全うした日本の偉人です。
※)田中芳男さんは、私の友人の曾祖父にあたります。
欲の無いこの愛すべき友人に代わって。
(彼こそ、小説や映画にすれば面白いのに。主人公は是非、堺雅人さんに。)